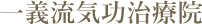低血圧の症状と原因
低血圧症には、原因不明の本態性低血圧と明確な病気や怪我による症状とに分類されます。後者の心臓疾患、腎不全、大量出血などによって引き起こされる低血圧症は、むしろ少数です。約9割の人が、前者の本態性低血圧に分類されます。ここではこの原因不明と言われる低血圧症について、言及します。
低血圧症と言われる一つの基準が、上下の上の血圧が常に100mmHgを下回るような数値の時です。疲れやすさ、倦怠感、肩こり、頭痛、立ちくらみ、冷え、食欲不振といった血行不良に付随する症状が出ます。また血行不良は多くの病気・症状の温床となります。低血圧は高血圧と比べて健康上の問題とはされ難いのですが、大きな問題が出てくる前に、改善しておきたい部分です。
原因不明と言われる本態性低血圧ですが、以下のような原因が考えられます。
・心臓の機能が弱い
血液を押し出すポンプの働きが弱いと、血圧を上げられません。明確な心臓疾患であれば、現代医療の検査の目で発見できます。けれど病気という訳ではなく、単に少し機能が弱い程度の問題であれば、見過ごされてしまいます。
・自律神経の問題
自律神経が適正に機能しなければ、身体の運営に支障が出ます。神経が正常に働いているか否かを厳密に検査するのは困難であり、原因として特定し難い側面があります。
・血管の太さ
血管が太ければ、同じ血流量であっても、血管にかかる圧力は低くなります。この場合には、血圧の数値を問題にする必要はありません。現代医療を中心にした一般的な常識では、数値だけを問題視しがちです。ですが身体には個人差があり、数値だけでは、その人の健康は測れません。
改善法 と 治療法
低血圧症を改善するためには、原因に応じた適切な対応が必要です。血圧を上げる薬でも、数値上のバランスは取れますが、問題が解決したわけではありません。体質自体をしっかりと改善していきます。
心臓の機能が弱いタイプでは、心機能を向上させる取り組みが必要です。身体はどのような機能でも、使わなければ衰えます。心臓は運動をして心拍数を上げる機会を持つ事で、鍛えられます。持続して運動する機会を設けてください。心拍数を一気に上げすぎるのも危険ですから、スパルタ式のイメージで鍛え上げるのではなく、ほどほどに上がった所で調整します。運動内容は走るまでしなくても、急ぎ足での歩行、力強いぞうきんがけなどでも、心拍数は充分に上がります。
また心機能が弱っている方には、ハートチャクラが弱っている傾向にあります。チャクラの機能低下は、周辺の身体機能低下を引き起こします。ハートチャクラの弱体化が原因の場合には、感情の起伏自体も弱くなる傾向があります。これは自分では、自覚し難い部分かもしれません。
自律神経に問題があるタイプでは、生活習慣の改善が基本になります。自律神経の働きを乱す、発達を阻害する要因は多岐に渡り、これをすれば良いと明確な傾向をお伝えするのも困難です。食生活、睡眠、運動、ストレス、冷えなど、日常生活上での思い当たる問題点を見つけ、改善していきます。
また臨床現場から見ると、こうしたタイプの方は、自律神経の乱れというよりも、その発達において問題があるケースが見受けられます。経絡や呼吸などの問題も背景にありますが、チャクラが正常に働いていない傾向が強くあります。チャクラは身体の正中線上に位置し、神経の根幹部分に大きく関わっています。大人になってからでも、改善が間に合わない訳ではありません。身体機能が正常に働けば、このような長年の不備も、取り戻してくれます。