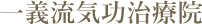気とは何か?
気とは誰もが持っているエネルギーです。気が存在しなければ、生命体は活動が出来ません。人間にとって気とは、身体を機能させるために必要不可欠なものです。ですから気功療法を行う事によって、身体が動的に変化します。精神や心も気が動きますが、これは人体の物質との兼ね合いの中で形成されます。実際の施術では、相応しい場所に軽く手を触れますが、これによって気の流れ・動きは志向性を持ちます。
経絡とは何か?
経絡とは人体を流れる気の道筋です。様々な道がありますが、その中で臨床的に重要な12経絡と奇経の督脈と任脈を合わせて、14経絡を採用しています。14経絡は、陰経と陽経の二種類に分けられます。陰経は身体の下から上に流れる経絡で、陽経は上から下です。両手は上げた状態で見ますので、指の先が一番上になります。一つ一つの経絡はそれぞれ役割があり、内臓の働きや血液や体液循環など、身体の動きの全てがカバーされています。他の経絡も多くありますが、流れは経絡と経絡で連動しますので、この14経絡に対するアプローチで身体全体をカバーできます。
- 肺経
外気を取り入れて、エネルギーを交換する。肺機能を司る。 - 大腸経
肺経と対をなし、外気を取り入れて、エネルギーを交換する。大腸の働きを司る。 - 胃経
気を取り入れ、消化する。消化器機能を司る。 - 脾経
胃経と対をなし、気を取り入れ、消化する。消化器機能を司り、特に膵臓と関連が深い。 - 心経
消化した気を吸収する。心と大脳の機能を司る。 - 小腸経
心経と対をなし、消化した気を吸収する。小腸機能を司る。 - 腎経
気の配分を受け持つ。精気、元気を貯蔵する。腎臓機能、生殖、老化を司る。 - 膀胱経
腎経と対を成し、気の配分を受け持つ。膀胱機能、生殖、老化を司る。 - 心包経
気を循環させる。心と心臓、血流を司ります。 - 三焦経
心包経と対をなし、同様の働きをする。体液の循環とリンパを司る。 - 肝経
気を貯蔵する。肝臓機能と血液調整、解毒を司る。 - 胆経
気を貯蔵する。胆のう機能、エネルギー調整を司る。 - 任脈
陰の経絡を統括し、未来への思いを司ります。 - 督脈
陽の経絡を統括し、過去の体験を司ります。
また経絡は気の道で、ここを経由してエネルギーや毒素が運搬されます。身体全体は気で繋がっており、エネルギーや毒素が身体を循環します。食べ過ぎで胃に負担がかかっている状態があったとして、大腸にも同様に負担がかかっていたとします。胃経の経絡調整を行った時に、そのエネルギーが循環していって大腸も同時に機能を回復させる場合があります。肺経の調整で腎臓・生殖機能が回復したり、他にも多くのケースが考えられます。
エネルギーの他に、毒素も運搬されます。これは特定の臓器に毒素が溜まり過ぎると機能障害が深刻になり、生命活動に重大な支障を起こすからです。ですから経絡を通して毒素を他の臓器に受け持ってもらい、排毒・解毒の役割を分け合います。心臓は止まると生命が停止してしまうので、毒素の受け持ちは最後の最後になります。また「膵臓が悪くて膝が痛くなる」「肝臓が悪くて目が疲れ易くなる」など、まったく関係がないと思われる箇所に症状が出るのは、気が毒素を運んで解消しようとした結果です。対応する経絡を治療する事によって、直接患部に触れていなくても、症状は改善します。食べ物が原因になるケースが多いので、脾経・胃経が毒素循環の出発点になっているケースは比較的多いです。勿論、受け持てる量にも限界があります。毒素を排出して減らしていく事をしなければ、やがては重篤な病にも繋がっていく危険性があります。
これは陰陽五行理論に基づく循環で説明ができます。陰陽五行論を理解する必要は必ずしもないので割愛しますが、気は全身を巡り、統合的に身体機能を動かしている事を覚えておいてください。