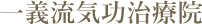心が健康な状態とは何か? おそらく一般的な感覚ですと、「前向きで明るい状態」といったイメージがあると思います。反対に不健康な状態ですと「落ち込んで鬱な状態」などといったイメージでしょうか。確かに前向きである事は創造性があってバイタリティーに溢れ、良い精神状態には違いありません。しかし良い精神状態=心が健康な状態というわけではないのです。
心が健康な状態とは、喜んだり悲しんだりといった喜怒哀楽が、豊かに正常に働く状態を指します。マイナスイメージの強い、悲しみや怒りなども、人間にとっては必要です。悲しみがあるから、また喜びもあります。悲しみがあるから、人間は自省を深められます。また怒りは爆発的なエネルギーを生み出します。危機的状況に対して、その爆発的なエネルギーを使って何とか切り抜けるのです。
悲しみ
ここで悲しみに焦点を当ててみます。その役割で大きなものの一つは、心のダメージに対する自律的な治癒作用です。心にダメージを受けると、私達はそれを悲しいと感じます。悲しみ自体がダメージのように受け取られますが、突き詰めれば微妙に異なります。風邪にかかって発熱をします。発熱自体は病気ではなく、病気を治そうとする自律的な治癒反応です。悲しみもこれと同じです。
心のダメージとは、喪失感であったり分離感や孤独感、劣等感や敗北感そのものです。それを悲しいと感じているのですが、悲しいと感じている事は即ち、それらのダメージを癒やしている状態となります。
そう言われても、今ひとつピンと来ないなと感じられている方も多いと思います。では過去に自分が悲しいと感じた事を思い出してみてください。その殆どは、悲しいと感じ続けているうちに、いつの間にか平気になっていますよね。これを考えると、悲しみ自体がダメージではないと何となく理解できると思います。悲しいと感じる事自体が、心を自律的に癒す手段となっているんです。
ですから悲しみから立ち直ろうとした時の正しい姿勢は、好きなだけ心に悲しませてあげる事です。無理やり前向きになっても、心はまだ痛んだままです。いつまでもウジウジ拘ってしまったり、更に反動でより深く落ち込んでしまう結果にもなります。悲しみという自浄作用が一段落すれば、心は自然と前向きになります。人間の心というものは、そのような仕組みになっているのです。
また落ち込んでいたけれども、ちょっとした切っ掛けで立ち直れたという経験は、誰でもあるでしょう。これも悲しんで悲しんで一段落がついていて、前向きに転換する準備が整っていた状況がそこにあります。何かがあって気分転換したとしても、準備が整っていなければ、一時的に気が紛れるといった程度で終わってしまうでしょう。
最後にポイントをまとめると、
①悲しみは心のダメージそのものではなく、心の治癒反応である。
②悲しむだけ悲しめば、心は自然と前向きに転換する。
③悲しみを何かで停滞させてしまうと、心のダメージはかえって癒されない。
悲しみ2
悲しみの一つの大きな役割は、心のダメージの自律治癒である事を書きました。それを少し深く考えてみます。
悲しみが心を癒すとは言うものの、悲しみが悲しみを呼ぶように、落ち込みが激しくなっていく事はよくあります。自律治癒どころか、余計に酷くなるじゃないか。だったら悲しまないように、何かで気を紛らわせた方が良いのではないか? このように考える方もいらっしゃるかもしれません。 悲しみは心のダメージの表面化でもあります。ダメージを癒すためには、潜在的なそれを自分が認知できるレベルまで引き上げる必要があります。そしてそれを悲しむ事で浄化させるのです。この引き出す過程で、人間は自分がどれだけダメージを負っていたかに直面しなければなりません。これが悲しみが悲しみを呼んでいる状態です。悲しみは治癒反応でありながら、主観的には苦痛を伴います。病気における症状と同様です。
こうして考えた時に、悲しむという行為は、正に自分自身を見つめる事と表現できます。楽しんでいたり喜んでいる時にはない、増してや怒っている時には起こり得ない、悲しみ独自の側面です。
悲しんでいる時には、当然そこに何らかの心のダメージがあります。それはもしかしたら、何かを失敗してしまった結果かもしれません。失敗とまで行かなくても、もっと上手くすれば回避できた事かもしれません。私達は悲しみを通じて自省を深め、経験から学ぶのです。例えば失恋してしまった時に、「独り善がりにならないで、もっと対話すべきだった。何でも解りきった気になっていた」と気づき、同じ過ちを繰り返さない用意が出来ます。こういった一つ一つが、精神的な成長や成熟となります。 もっとも、その分析が正しい保証はどこにもなく、その人には更に勉強の機会が必要となるかもしれません。またそのようなズレも多いものです。悲しみはあくまでも機会であって、成長という結果を保証するものではありません。では分析が的外れになってしまうのは、どのような時でしょうか。
それは悲しみから逃げた時だと、私は思います。先程の失恋のケースで考えてみると、独り善がりな姿勢が大きな側面としてあったのに、自分の落ち度を見つめる内省から逃げて「結局相性が悪かったという事だな」とか、「俺の魅力が理解できない女は、こっちから願い下げだ」とやると、また同じような過ちを繰り返す事になります。何度か失恋を繰り返す内に、ようやく「自分に何か原因があるんじゃないか?」と気づくかもしれません。それが悪いというわけではなく、その人にはそれだけの機会が必要だったのでしょう。
解り易い例として失恋を挙げましたが、細かい小さなものを含めると、私達は実に多くの悲しむ機会に恵まれています。仕事で失敗した時、誰かを怒らせてしまった時など。その都度、私達はしゅんとし、内省をするのです。この内省は意識して行うものではなく、半ば悲しみとセットになっている自動的なものです。勿論意識をすれば、更にこの内省を深められます。そこで思い上がりはなかったか、自己中心的すぎではなかったか、忙し過ぎてストレスが溜まっていたのではないか、など多くの気づきを得ます。その度に小さく、あるいは大きく軌道修正が行われ、人間は成長していきます。
悲しみとは人間にとって、心を癒すための作用であると同時に、精神的な成長や成熟を得るための呼び水でもあるのです。精神的な成長は、整然とした建築のイメージでは捉えられません。何度も破壊と再生を繰り返しながら、時には歪み、時には修正され、次第に成熟していくものです。一生をかけて、一つの芸術作品を創り続けているようなイメージが近いかもしれません。完成形もまた存在しません。
まとめると、
①悲しみは自動的に内省を促す。
②内省によって自分をより深く知り、それを修正する機会を得る。
③悲しみは、人間が精神的に成長・成熟していくための呼び水である。
となります。
怒り
怒りは一般的に「防衛」として捉えられています。悲しみは心の自律回復のための反応として出ますが、これは苦痛を伴います。心に負ったダメージが深すぎて、悲しみに押し潰されてしまいそうになった時に、怒りという感情に変わります。失恋した時に、悲しくて悲しくて仕方がなくて、急に相手の落ち度を見つけて怒り出す事は珍しくありません。「あんなに親切にしてやったのに、恩知らず!」といった具合です。
怒りのエネルギーは凄まじく、悲しみによる落ち込みを高揚で吹き飛ばすには十分です。そのような時には、悲しみと向き合えるようになるまで、もしくは悲しむ必要がなくなるまで、怒りは継続されます。また人間は傾向として、自尊心が危機に陥った時に、怒りで防衛する場合が多いようです。怒りは人間の強さではなく、人間の弱さを表現します。
ここで特筆したいのが、怒りは悲しみによる「落ち込み」を吹き飛ばすのであって、悲しみそれ自体を吹き飛ばすわけではないという事です。悲しみは心の傷を修復させるものですから、吹き飛ばしてしまっては意味がありません。怒りによる高揚は、より多くの悲しみに耐えられる精神環境を整えているのです。ですから怒っている時には、より強く深い悲しみにいる傾向があります。
防衛以外にも、人間は怒るのではないかと私は考えます。それは爆発的なエネルギーが必要となる場面です。例えば子供が危ない場所に近づいた時に、親は血相を変えて怒り、子供を叱る場面があります。これは子供に危険であると強烈に印象づけるため、それだけの多量なエネルギーが必要であるという事です。また自分の不甲斐なさに怒った事は、皆さん何度か経験されていると思います。無気力で堕落した生活を送っている時に、「何をやってるんだ、自分は!」と何かを切っ掛けに急に奮い立つ。そのような状況を変えるためには、ロケットが発射する時のような爆発的なエネルギーが必要となるのです。
まとめると、
①怒りは自己防衛のための反応である。
②怒りは爆発的なエネルギーが伴う。
②自己防衛以外にも、爆発的なエネルギーが必要な場面で、怒りは湧き上がる。
となります。
喜び、楽しみ
喜びと楽しみは、心のOKサインです。その状況が心や身体にとって良い事であると、プラスの感情で反応します。ですから人間は、喜びと楽しみを自然と求めます。人間は誰もが、多かれ少なかれ快楽主義者です。
ところが快楽主義は常に、あるべき姿から歪む危険性に晒されています。苦痛から逃れる手段としてある快楽は、その度合いが高い。ギャンブル依存症やアルコール依存症などは、その解り易い典型です。ギャンブルやアルコールは人間に高揚感をもたらします。ですがそれは、人間の実生活に沿わない、虚構の世界での高揚です。 ギャンブルでは、勝つ・負けるという結果は究極的にはどうでも良い事で、リスクをとって勝負をしている事実そのものが重要となります。その高揚感が、実生活上の苦痛から目を逸らせたり、普段の暮らしでは得られない刺激となります。アルコールは抑圧された感情を解放します。笑う人、怒る人、泣く人、それぞれが普段抑圧されている感情を放出させています。
ギャンブルやアルコール自体が、必ずしも悪いというわけではありません。趣味などでも、人間は補助的な作業によって心のバランスをとっています。問題なのは、それがコントロールを離れ、依存症という形にまで陥ってしまう事です。
実生活上で、健全に喜びや楽しみが見出せれば、そのような中毒に陥ってしまう事は起こりません。では喜びや楽しみは、どうすれば見出せるのでしょうか? 私はその秘訣は、生活の中でメリハリをつける事だと思います。人間の心は、常にギャップの大きさに反応します。お腹が空いている時の食事は幸せそのものですが、そうでもない時には、やはり幸福感も乏しいものです。普段は仕事で忙しい人が、温泉旅行でゆったりとすれば何とも言えない充足感でしょう。しかしいつも暇な人が同じようにゆったりしても、そのまま「退屈だなあ」という感想になるかもしれません。
一日の中で、あるいは一週間や一月の中で、変化に富んだ生活を送るようにする事が、喜びや楽しみという感情を豊かに保つには必要です。ギャップがなくなると、人間は何も感じなくなってしまうのです。そのくせ退屈は苦痛として認識しますから、何となく生きていてツマラナイ。だから外的な刺激が必要になってきます。
またストレスが多い生活をしていると、その防衛反応で感受性自体を弱めてしまいます。まともにストレスを受け止めていては、心身がもたないからです。何か精神に強い衝撃を受けても、同様の現象が起こります。喜んだり楽しんだりする感受性も一緒に弱められるので、何をしてても楽しくないといった状態に陥ります。通常でしたら、今はその感受性を解放しても良いんだという場面で切り替えが行われますが、ストレスがかかり過ぎると切り替えも困難になってしまいます。結果として、生活上で精神的なギャップも平坦なものになります。
こうなると少しの事では、心は反応してくれません。ですからより強い刺激を求めて、上記のギャンブルやアルコール、ドラックやセックスに走って依存するようになるのです。そして堕落は新たなストレスとなるので、状況は悪循環になります。
道に咲く花や青空を美しいと感動する。食事に美味しいと感激し、命や作り手への感謝が自然と芽生える。何と言う事はない些細なギャップを感じ取って喜びや楽しみと出来る精神状態が、本来あるべき姿ではないでしょうか。そのような豊かに反応する心を持っていれば、強い刺激を求める必要もないのです。
まとめると、
①喜びや楽しみは心のOKサイン。 ②何かの依存症による快楽は、虚構の刺激。
③ストレスや衝撃によって、人間は感受性自体を弱めてしまう。喜びも楽しみも感じ難くなる。
④豊かな感受性で、些細な事に喜びや楽しみを見出せる状態が正常。
となります。
恐怖
喜怒哀楽それぞれについて考えてきましたが、今回は別の視点に移りたいと思います。 人間はおぎゃあと産まれる前から、その命は始まっています。胎児時代からの経験の積み重ねによって、様々な学習をしていきます。子供がワガママを言ったりすると、親や先生から「ワガママを言うんじゃない」と叱られます。またワガママだと友達から嫌われたりするので、自然と「ワガママはいけない。他人に合わせる事もしないと」と学習するわけです。この場合は、ワガママを言うと不利益を被るという情報が入力され、ワガママが禁止事項として記憶された形になります。人間は死ぬまで、このような学習を繰り返します。
しかしその全てが理に適っているわけではありません。不適切、もしくは特別な体験によって、誤った学習をしてしまうケースも多いのです。例えば母親から捨てられた子供が、その原因を「自分が良い子にしていなかったからだ」と解釈したとします。結果、その人は誰に対しても本当の自分を出せずに、過度に良い人を演じ続ける大人に成長するかもしれません。そうしなければ、自分は捨てられてしまう脅迫観念に囚われているのです。騙された衝撃を強く受けた人間は、猜疑心の強い性格になりがちです。騙される事を過度に警戒します。
このようにして、人間には様々な禁止事項や恐怖の対象が形成されます。その形成が子供時代のものであれば、位置付けや感じ方の修正はより困難になります。また子供時代の衝撃は、その人の精神的な成長を歪ませてしまう危険性を孕んでいます。
大人になってからの体験であれば、例えば恋愛で酷い体験をしたとしても、すぐに「それはたまたまで、今度の恋愛は大丈夫だろう」という判断が出来ます。恋愛をすると酷い目に遭うと印象づいたとしても、それを最小限に留め、追体験によって修正が可能です。ところが子供時代のそういった誤学習は、印象により強く刻まれる上に、大人になったら何が何と結びついて恐怖の対象になっているかも自覚できないケースも多く、問題はより複雑になります。
潜在意識レベルでの問題は、多くの場合、無意識下で意味付けの更新が行われます。普通に暮らしていれば、普通に色々な体験をします。それが自動的に追体験となり、印象は常に更新され続けます。ところが衝撃が強いそれは無意識的な更新が追いつかず、鬱や神経症などの心の問題に発展します。
全体のバランス
こうして考えてみると、心が健康な状態とは、特定の感情が突出する事によっては得られない物であると理解できます。良い事があったら喜び楽しみ、悪い事があれば悲しむ。時として怒る場面もある。このように感情が豊かに揺れ動き、それぞれの役割を果たしている状態が健康な精神の在り方です。
ですから、無理に前向きであり続ける必要はないですし、それはむしろ不健全な姿です。前向きでいようとしなくても、精神が通常の働きをすれば自然と前向きになります。その過程として、落ち込んで後ろ向きになっている状態が必要なんです。わざわざ特別に意識しなくても、私達人間は前向きに出来ています。
何かショックを受ける出来事があって、例えばすぐに「良い勉強になった。これを教訓に前に進もう」と方向づける人がいたとします。よく見受けられる行動です。しかしこれは悲しみや怒りの段階を意識的に省略して前向きになっているので、歪が出ます。潜在意識ではその衝撃はまだ消化されておらず、前を向ける段階ではないのです。 人間にはそれぞれ、ここまでは大丈夫という衝撃に対する限界があります。上手く消化していかないと、その限界までに余裕がない状態となり、今度は衝撃をまともに受けないような防衛が必要となってきます。結果として怒りっぽくなったり、自分の都合の良い意味づけでしか、物事を呑み込めなくなります。それは現実を現実として受け取らず、虚構の世界で生きていくようなものです。
このように、過度に前向きになろうと意識する事は、人間を歪ませてしまうのです。ですから表面的には明るくて前向きな人が、お酒でも入って少し本音が出ると、実は虚しさに苦しんで必死に戦っていたりします。そしてその状態をまた前向きに解釈するために、「顔では笑っていても、本当は皆苦しくて、心の中では泣いているんだ。自分だけが苦しんでいるわけじゃないんだ。だから頑張るんだ」といった受け取り方をしていたりします。勿論、「皆が」という事実はないわけです。
怒りたくても、怒れない人がいます。立場上の問題もあるかもしれないし、他人に対する評価を気にするせいかもしれません。社会人として、好き放題怒るのも考え物です。しかしその時に心は怒りを必要しているのは間違いありません。怒りは心を守る防波堤の役割をします。怒りを解放させる場面がないと、やがてはそれが大爆発してしまうケースもよくあります。普段大人しい人が、キレて大暴れしたりしますが、これは正に限界間近まで追い詰められて、一気にそれを跳ね付けようとした結果でしょう。
怒りもある程度、コントロールできます。皆の前では我慢して、部屋でこっそりと爆発させたりもできます。またここは怒っておこうと、状況を見て冷静にその感情を許す事も出来ます。
感情のコントロールという話では、実は喜怒哀楽全てにおいて、当然ある程度それが可能です。責任ある立場になれば、感情の赴くままというわけにはいきません。上手にコントロールをして、自分の精神を健全に保つ意識が必要になってきます。ですから意識をして、喜んだり楽しんだりして良い時にはそれを満喫し、悲しんだり怒ったりして良い時にはそれを解放します。
それぞれの感情には役割があって、心は循環するものです。心は循環する事によってバランスを保ち、成長し、成熟するものです。
また人間は、怒りや悲しみであっても、それを快感とする部分があります。実生活上の悲しい出来事は、多くの場合、実害があるのでそれを感じ取れる余裕がありません。快感は存在していますが、それを認知できないのです。悲しいのは嫌なはずなのに、わざわざ悲しい泣ける映画やドラマを観るのは何故でしょうか。それは悲しみ自体に快感が伴うからです。
快感なくしては、ただ辛いだけでは人間は悲しもうとしません。そこに快感が存在するから、悲しむという状態に突入できるのです。快感は悲しいという状態に導くためでもあり、また辛さに潰されてしまわないための救いでもあります。
怒りも同様で、その興奮状態は快感です。エネルギーに溢れ、生命が燃え上がるような感覚があります。腹立たしいのが解っていて、わざわざニュースを観ては怒っている。こんな場面にもよく遭遇します。これは怒りに快感が伴わなければ、起こり得ない事です。
実はそのような、実生活には直接関係のない悲しみや怒りによって、人間は救われてバランスを取っている側面があります。悲しい映画を観て涙しながら、人間は自分が負っている心の傷を同時に癒しているのです。潜在意識がその悲しいポイントを、象徴的に受け取る結果です。象徴的に連想関係にある時、擬似的な悲しみであっても、心の傷は癒されます。また悲しんだり怒ったりする行為自体が、心のダイナミズムを生み出します。心を活発化させる意味でも、人間は悲しみや怒りに揺り動かされる事を求めるのです。
そのタイナミズムを求める側面では、コメディーやバラエティー番組などで笑う事も同じ意味を持ちます。人間はその時々で必要で不足している感情を、擬似的に補っていくのです。
心は健全であろうとするために、ダイナミズムの維持が重要です。感情を豊かに表現させる事そのものが、健全な精神状態に繋がります。自分はこういう人間でありたいと、理想の自分像を持つのは良い事です。しかしそれが「~でなくてはいけない」という強迫観念になった時には、歪んでいくものです。
色々な感情を持つ事を自分に許せ(認めれ)ば、結果として自分で嫌だと思う部分は、その勢力を弱めていきます。どんな醜い感情であっても、それは必要だからそこにある。その感情を経過しなければ、到達できない領域があるのです。
最後にまとめると、心が健全な状態とは、一見不健全だと思われる心理や感情を認め、心が上手に循環していく事によって得られるものであると言えます。