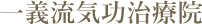味覚障害の原因は、様々
味覚障害という症状は同じでも、そこに至る原因は様々です。また味覚障害にも、種類があります。味が薄くなる、味がなくなる、甘みだけが判らない、本来 とは異なる味に感じるなどです。
① 亜鉛欠乏
亜鉛が不足する事により、細胞の新陳代謝が低下します。味蕾の味細胞はその新陳代謝が活発で、10日サイクルで入れ代わります。亜鉛不足で新しい細胞を 作り出せず、味覚障害に至ります。
亜鉛が不足する原因としては、偏った食生活や過激なダイエットなどが挙げられます。また食品添加物も要注意です。体外へ 亜鉛を排泄するもの。亜鉛の腸管での吸収を妨げるものがあります。お酒の飲み過ぎも良くありません。アルコールの分解に、亜鉛を大量に消費します。
② 心因性
精神的な問題で、味覚を感じられなくなる。または味覚が変化してしまう事があります。現実を直視したくないという感情があるのか、他人とのコミュニケーション に苦痛を感じていないか、その他大きく負担になっているものはないか、自分自身を見つめてみましょう。
③ 薬剤性
薬剤の中には、亜鉛と結合して外に出してしまう副作用を伴うものもあります。亜鉛の欠乏から、味覚障害に至ります。
④ 嗅覚障害
鼻をつまんで物を食べると、味が判らなくなります。味覚障害の正体が、嗅覚障害であるケースもあります。代表的な例が、風邪の時に味が判らなくなる現象です。
⑤ 病気に伴うもの
糖尿病、肝疾患、貧血、膠原病、内分泌機能低下などの全身性の病気から、味覚障害に至るケースがあります。
改善、対策
亜鉛を多く含む食品の摂取、食生活の改善、亜鉛の服用で、多くの方の症状は改善します。病気に伴うものであれば、その大元の病気の改善が必要になります。 心因性のものも、精神的な課題の克服、ストレス源を遠ざける、などがなければ、改善はやはり難しくなります。
精神的な問題に取り組む際にも、病気を治す際にも、その部分だけを見ては行き詰るケースも多く出てきます。心身を統合的に全体として向上させていく、広い 視野をもって取り組んでいくべきです。