更年期障害は、特に女性にとって避けられない重大な問題です。心身のバランスが崩れ、重症化すると日常生活に多大な支障を来たします。今回の記事では、更年期障害とは何か?症状とどう上手く付き合い、軽く済ませられるのか、について解説していきます。
女性更年期障害の症状
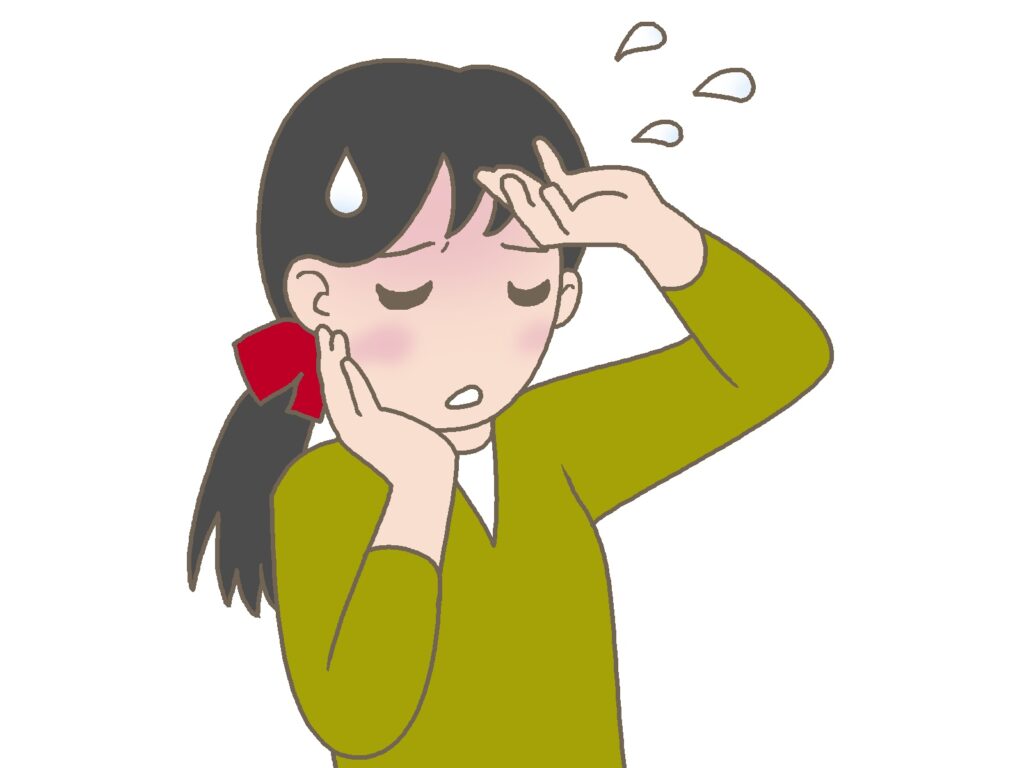
症状の意味
女性の更年期障害は、一般的には、閉経期前後の45~55歳頃に起こります。エストロゲン(ホルモンの一種)が減少し、ホルモンバランスが崩れる事で発症します。 脈が速くなる、動悸、めまい、血圧の不安定、耳鳴り、微熱、生理不順など、多くの症状を引き起こします。
閉経時期は、もう子供を産む準備をしなくても良いと、卵巣の活動性がだんだんと失われていき、身体が大きく変わる時期です。身体は常に、健康であろうとします。今度は子供を産まない事を前提にしたシステム に切り替えようとするのです。切り替えは、そうそう簡単にはいきません。生理には体内毒素を排出する大きな役割も兼ねられていたのですが、その手段を一つ、失う事になります。全体のバランスが崩れて、新しい体制が整えきれない。これが更年期障害の姿であり、症状の意味になります。
具体的な症状
更年期の症状の内容、症状の重さには個人差があり、全てが自分に当てはまるというものではありません。実際に更年期症状には100種類くらいあると言われており、その症状は非常に幅広いものとなっています。
ここでは、主な症状をご紹介していきます。
身体的な不調
1,頭痛
更年期障害の頭痛の症状は、頭全体を締め付けるような痛みが続くものです。ホルモンバランスの変化による頭痛は、痛みが強い傾向にあります。
2.肩こり
エストロゲンは血管を拡張させ、血流を良好に保つ働きがあります。また、筋肉の緊張を緩和する作用も持っています。エストロゲン分泌の減少は、これらの作用を弱め、血管が収縮しやすくなり、血流が悪化します。結果として、肩こりに繋がります。また同ホルモンの分泌減少は、自律神経を交感神経優位にさせます。これも筋肉を硬くさせる原因になります。
3,腰や背中の痛み
理屈としては、肩こりのご説明と同じです。血流悪化と筋硬直が重症化すれば、痛みを感じるに至ります。勿論、軽度ではコリとして感じます。
4,関節痛
肩や手足、膝にこわばりや腫れの症状が出てきます。関節痛は、関節リウマチと症状が似ています。症状が強く出ている場合には、更年期だからとスルーせず、医療機関を受診してください。
5,しびれ
女性ホルモンの減少による血行不良や筋肉の緊張が、しびれを引き起こします。手足のしびれのほか、皮膚の表面が乾燥した時のようにピリピリと感じるというのも、その症状の一つです。
精神的な不調
1,イライラする
エストロゲンの減少によりセロトニンが不足すると、感情のコントロールが難しくなり、イライラしやすくなります。また、身体の不調もイライラの原因となることがあります。
2,不眠
ホルモンバランスが崩れ自律神経が乱れることで、のぼせやほてりが生じ、不眠を引き起こします。また、セロトニンの減少により気分が落ち込みやすくなり、不安感が増して睡眠の質を低下させることがあります。
3,やる気がおきない
エストロゲンが減少すると、意欲が低下し精神が不安定になります。意欲が低下し、物事に積極的に取り組む気力が失われやすくなります。
4,情緒不安定
女性ホルモンが減少すると、不安を感じやすくなったり気持ちのコントロールが自分の思ったようにできないということを招きます。それに気分の波が激しくなったり、急に涙が出たりするということが出てきます。
血管運動症状
1,ほてり・のぼせ
エストロゲンの減少により自律神経が乱れ、血流が悪化して体温調整が困難になることで発生します。
2,ホットフラッシュ
突然の体温上昇や心拍数の増加、顔や首の赤みが特徴です。症状後には体温が急降下し、冷えや震えを伴う場合があります。
3,発汗
暑くない状況でも急に大量の汗をかき、睡眠中にも発汗することがあります。
4,冷え
自律神経の乱れで血行が悪化し、体温維持が難しくなることで冷えが生じます。足先や指先が冷えたままになり、不眠やその他の健康被害に繋がるリスクもあります。
症状を軽くするには?

ご覧いただいてわかるように、女性の更年期障害の症状は身体のさまざまな箇所に起こり得るものであり、また精神的な不調を引き起こす場合もあることから、心身ともに大きな負担となってのしかかるものであるといえます。
少しでも更年期の症状を改善し、心身の状態を保つためにできることにはどのようなものがあるのでしょうか?
食生活の改善
ホルモンバランスを整える食事のポイント
1. 大豆製品の積極的な摂取
- 大豆イソフラボンはエストロゲンに似た働きをする成分で、更年期の女性におすすめです。
- 豆腐、納豆、豆乳などを日常的に取り入れることで、ホルモンバランスをサポートできます。
2. カルシウムを豊富に含む食品
- 骨量が減少しやすい更年期には、カルシウムが重要です。
- 牛乳やヨーグルトなどの乳製品、小魚、海藻類を積極的に摂取しましょう。
3. 緑黄色野菜と副菜
- ビタミンやミネラルが豊富な緑黄色野菜(ほうれん草、ブロッコリーなど)は、新陳代謝を促進し、体調維持に役立ちます。
- 副菜として野菜や海藻類、きのこ類を取り入れることで栄養バランスが整います。
4. 青魚やナッツ類
- 青魚(サバ、イワシなど)はDHAやEPAが豊富で、ホルモンの働きを助けます。
- ナッツ類はビタミンEが豊富で抗酸化作用があり、体内環境を整えます。
5. バランスの良い和食メニュー
- ご飯と味噌汁、魚料理、おひたし、煮物などを組み合わせた和食は栄養バランスが良く、更年期に適しています。
冷え取り健康法
体の冷えは更年期障害を深刻化させるだけでなく、その他の心身のトラブルを引き起こします。体の冷えを取り、血流を良く保ちましょう。
基本は、毎日の入浴習慣です。38~39度の温度設定で、最低でも30分は浸かるようにしてください。温度設定が高いと体の奥に熱が浸透せず、芯が冷えたままになります。胸の前が空いていれば、半身浴でも仰向けで背中が湯につく形でも大丈夫です。
また寝る時、締め付けの少ない天然素材の靴下で足を保温しましょう。絹、綿、絹、綿と重ね履きをすると、足元の排毒効果が高まります。この時、足元に湯たんぽを置くのもお勧めです。
適度な運動
適度な運動、特に有酸素運動はエストロゲンの分泌を助けます。またホットフラッシュ、不眠、動悸など、更年期特有の症状を緩和する効果が期待できます。楽しく行えば、自律神経の調整にもなり、体はもちろんメンタルの調整にも役立ちます。
ジョギング、ウォーキング、サイクリング、水泳など、有酸素運動には多くの選択肢があります。無理なく楽しく続けられるものを選んで、日々の習慣になさってください。一回30分程度、週に3回くらいがお勧めです。
自分に合ったリフレッシュ法
病は気からと言いますが、メンタルと体調は密接につながっています。日々の生活の中で、自分を楽しませる習慣を取り入れてください。
その中身については、人それぞれです。運動、映画鑑賞、美術館や博物館に行く、カフェでおしゃべり、など楽しければ何でも大丈夫です。更年期の症状があまりに辛くて、何かを楽しむどころじゃない!という時もあるかもしれませんが、ちょっと頑張れば……くらいなら動いた方が良いです。
但し、タバコやお酒など、健康と引き換えにするようなものは、絶対にダメとは言いませんが、一定の節度の中で楽しむようにお願いします。
休息と睡眠を大切にする
何かやる事があると、睡眠時間を削って調整する。そんな癖があるなら、そろそろ健康的な生活習慣にシフトチェンジしましょう。
心身の健康は、毎日の睡眠に支えられています。そこで集中的にメンテナンスを行い、リフレッシュして次の日を迎える。このサイクルが崩れると、次第に借金が膨らむように健康が害されていきます。
また寝つきが浅い、早く目覚めてしまう、という人は、自律神経を軸に睡眠を考えてください。眠るときには、副交感神経に深く入ってリラックスしている必要があります。日中に精力的に活動して肉体にはほど良く疲労感があり、大きな悩みや心配事はなく(あっても、あまり気にしない)、寝る時間の4時間前には電気を暗くして脳を興奮させる活動は避ける。これを意識するだけで、かなりの眠りの課題は改善されます。
一義流気功では、どう対応するの?

更年期障害には、この治療!はありません
更年期障害は、肉体に起こる必然です。ホルモンバランスが変わって、新しくバランスを取り直す過渡期です。ですから異常ではなく、実は治す対象ではありません。一義流気功においても、更年期障害には必ずこの治療というセオリーはありません。
発想は、いかにスムースにこの段階を過ぎ去らせるかです。
潜在意識から情報を引き出す
潜在意識から情報を引き出すと、更年期だからと特別な要望はなく、概ね通常と同じ治療法や日々の取り組みがリクエストされます。ただ食生活については、ホルモン分泌を意識する方向性も出てきます。
更年期障害だからと何か特別なことするのではなく、普通に健康に良いことは更年期障害にも良いとお考えください。
まとめ、結論
更年期障害は、ホルモンバランスが変わる過渡期です。様々な症状が出てきますが、ここを「これからの人生、もっと健康に気を付けよう!」と考え直すきっかけにしてください。食生活、運動、睡眠、ストレス軽減など、健康に良いものは総じて、普通に更年期障害にも良いです。
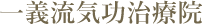
公式HP https://ichigiryu.com/about/
住所〒116-0002 東京都荒川区荒川 6-52-1 1F
電話番号03-6427-7446 / 090-6499-9762(直通)
営業時間午前10時~午後8時(電話受付:午前10時~午後7時)

コメント