不定愁訴とうつ病とは、時として症状が混ざり合い、区別に難しいケースもあります。この記事では、不定愁訴とうつ病との症状の違いを明確にし、それぞれの治療法やセルフケアについてお伝えします。
不定愁訴とうつ病の違い

不定愁訴には、うつ病になる前にあらわれる初期サイン(前駆症状)とよく似ている部分があります。前駆症状とは、病気が本格的に始まる前に出てくる軽い症状です。ここでは、不定愁訴と、うつ病の初期に見られる症状の違いについて、わかりやすく説明します。
不定愁訴によく見られる症状
不定愁訴は、原因がはっきりしないまま全身に様々な不調が現れます。体がだるい、疲れやすい、頭痛や肩こり、冷え、便秘や下痢、めまい、むくみといった身体的な症状のほか、イライラや気分の落ち込み、眠れないといった精神的な不調もみられます。これらの症状は一つだけが長く続く場合もあれば、複数の症状が不定期に現れることもあり、人によって現れ方や程度は様々です。
検査を行っても原因は判明しないのが特徴で、というより、そのようなものを『不定愁訴』という括りに入れているのが実情です。
うつ病に現れる前駆症状
うつ病の初期段階では、身体に以下のような前駆症状が現れます。倦怠感・体のだるさ・疲れやすさ、睡眠障害(寝つきが悪い、途中で目が覚める、早朝に目が覚めるなど)、食欲不振や体重減少、頭痛や肩こり、めまい、胃の不快感、吐き気、消化器症状(下痢・便秘など)、胸の動悸、寒気、手足のしびれ、口の渇き、など。
またメンタルでは、落ち込みや憂鬱さを感じ始め、楽しめたことが楽しいと感じなくなる、何をするにもやる気が出ない、意欲の低下、イライラして怒りっぽくなる、集中力や思考力の低下、マイナス思考、自分を責める、自己評価の低下、といった変化が現れます。人と会うのを避けたり、外出や身だしなみに無頓着になるなど、行動や生活態度にも変化が出ています。
不定愁訴とうつ病との共通点
こうして並べてみると、両者には多くの類似性があると解ります。例えば、体がだるく疲れやすい、肩こりもして頭痛もするし、下痢も続く。元気がなく、気分が冴えない。といった状態の時、それが不定愁訴なのかうつ病なのか、見極めるのは非常に困難です。
見分けるためのポイント
不定愁訴とうつ病を見分ける際、以下のようなポイントがあります。完璧にという訳には行きませんが、大きな判断材料になります。
肉体と精神、どちらの症状が強いか?
うつ病の場合は、「気分が落ち込む」「何をしても楽しくない」「意欲がわかない」といった精神的な症状が強く出ます。これらが2週間以上続き、日常生活に支障が出るようなら、うつ病である疑いが濃くなります。一方、不定愁訴は身体の不調が中心で、精神症状が目立たない場合が多いです。また、うつ病の精神的な症状は、朝に強く現れる傾向があります。
精神症状も肉体症状も同時に現れている時、その比重、うつ病の特徴との合致で判断できます。
落ち込みが、短期的な休息で改善するか?
うつ病を改善させる主な取り組みは休息ですが、回復は中長期的に見なければなりません。一日や二日、ゆったりと休んで気分が大きく回復するようなら、それはうつ病の症状ではなく、肉体疲労によって元気がなかっただけと判断できます。
早期発見をするには?
不定愁訴
不定愁訴を早期に発見するには、日常生活の中で自分の体調や気分の変化に目を向ける意識が大切です。「なんとなく体調が優れない」「原因不明の不調が続く」と感じたとき、年齢や体質のせいと決めつけず、普段と違う症状を振り返ってみましょう。セルフチェックリストを使い、「十分に休んでも疲れが抜けない」「寝つきが悪い」「食欲が落ちている」「イライラしやすい」「集中力が続かない」「手足が冷える」など、複数の項目が当てはまる場合は注意が必要です。
また、生活習慣の見直しも早期発見につながります。睡眠や食事、運動のバランスが崩れていないか、ストレスが溜まっていないか、趣味やリラックスできる時間を持てているかなど、日々の暮らしを振り返ってみましょう。こうした自己観察やセルフチェックを習慣にすることで、不定愁訴のサインに早く気づきやすくなります。
不定愁訴のセルフチェックリスト
- 寝つきが悪く、眠りが浅い
- 食欲がない、または何かを食べていないと落ち着かない
- 食後に胃の痛みを感じることがある
- しっかり休んでも体の疲れがとれない
- やらなければいけないことがあるのにやる気が出ない
- 漠然とした不安を感じて落ち込む
- 集中できない
- 風呂上がりなどでも手足が冷える
- 1年間で5kg以上太った/痩せた
うつ病
一方、うつ病を早期に発見するポイントは、気分の落ち込みや何をしても楽しめないといった精神的な変化が2週間以上続いたり、興味や意欲の低下、集中力の低下、睡眠障害、休んでも取れない疲労感などが現れ、日常生活や仕事に支障が出てきた場合です。本人が気づきにくいことも多いため、周囲が「いつもと様子が違う」と感じたときも早めに専門医を受診することが重要です。
うつ病のセルフチェックリスト
- 何をしても楽しいと感じられない、または興味が持てない
- 気分が落ち込む、憂うつになる、絶望的な気持ちになる
- 寝つきが悪い、途中で目が覚める、逆に寝すぎてしまう
- 疲れやすい、体がだるい、気力が出ない
- 食欲がない、または食べ過ぎる
- 自分に自信が持てず、価値がないと感じる
- 集中できない、物事に注意が向かない
- 動作や話し方が遅くなったり、反対に落ち着きがなくなる
- 死について考えたり、自分を傷つけたいと思うことがある
医療機関での対応

不定愁訴に対する医療機関での取り組みは、従来の薬物療法や検査だけでなく、心身両面からの総合的なアプローチが重視されています。
不定愁訴は、心身両面からアプローチ
不定愁訴の治療では、まず身体的な疾患が隠れていないかを丁寧に調べ、検査で異常がなければ心身両面から総合的にアプローチします。薬物療法では、睡眠薬や抗不安薬、抗うつ薬、漢方薬などを症状に応じて使い分け、東洋医学的な視点も取り入れています。
さらに、心理療法やカウンセリングも積極的に行い、ストレスや悩みの解消、セルフケアの方法などをサポートします。最近では、リラクゼーション法や自律神経のバランスを整える治療(頭鍼やマッサージなど)を取り入れる医療機関も増えています。
患者への説明や対話も重視されており、納得したうえで治療に取り組めるよう配慮されています。また、女性外来や総合診療科などの専門外来を設け、性別やライフステージに合わせたきめ細かな対応も行われています。このように、薬や検査だけに頼らず、心と体の両面から多角的に支える医療が主流となっています。
うつ病は、精神薬とカウンセリング
うつ病の診療では、まず精神科や心療内科、メンタルクリニックなど専門の医療機関で診察が行われます。初診時には、患者の精神的・身体的な症状や生活状況について丁寧に問診し、必要に応じて内科的な検査も実施されます。軽度の場合は身近な内科で相談・検査を受け、必要に応じて専門医へ紹介されるケースもあります。
治療の中心は、薬物療法と心理療法(カウンセリング)の組み合わせです。薬物療法では抗うつ薬などを用い、気分の安定や再発予防を図ります。心理療法では、認知行動療法や対人関係療法などを通じて、考え方や行動パターンの改善を目指します。患者の状態に応じて、両方を併用したり、軽症の場合は心理療法のみで対応することもあります。
また、家族や周囲のサポートも重視されており、受診や治療への付き添いや、必要に応じて家庭訪問や地域の支援機関と連携した対応も行われています。患者が安心して治療に臨めるよう、わかりやすい説明や継続的な支援が心がけられています。
頼りは、自然治癒力
不定愁訴にしても、うつ病にしても、実は医療の力で明確に治せるものではありません。不定愁訴は、正式には不定愁訴症候群と言い、症候群とは「よく解らないけど、〇〇という状態」という意味です。必要に応じて症状を薬で抑えながら、生活習慣や心の在り方を修正し、自然に改善するのを待つという形です。
一方、うつ病も同じような取り組みです。精神薬で症状を緩和させながら、休息によって回復を待ちます。並行して、考え方や価値観の歪みでストレスを余計にかけているなら、認知行動療法などでそれを修正します。
ですから不定愁訴にしても、うつ病にしても、セルフケアの重要性は極めて高くなります。
自宅でできるセルフケア

不定愁訴を改善するセルフケア
不定愁訴を改善するセルフケアには、主に生活習慣の見直しとストレス対策が効果的です。健康的な生活を送りながら、自律神経を整えていくのが基本の柱です。
日光浴と生活リズムの整え方
日の光を浴びることでセロトニンの分泌が促され、感情のバランスを整える効果があります。また、就寝時間と起床時間を一定に保つことで生活リズムが安定し、睡眠の質が向上します。
食生活
栄養バランスを意識し、特定の栄養素や食品を積極的に取り入れることがポイントです。まず、たんぱく質やビタミンB群、ビタミンD、鉄、カルシウム、亜鉛などの不足を防ぐため、肉や魚、卵、大豆製品、乳製品、緑黄色野菜、海藻、ナッツ類をバランスよく食事に取り入れましょう。特に青魚に多いDHAやEPAは血行を良くし、ビタミンB群やEは神経や自律神経の働きをサポートします。
また、腸内環境を整えることも自律神経の安定やセロトニン分泌に関係するため、ヨーグルトや納豆、味噌などの発酵食品や食物繊維が豊富な野菜・果物・雑穀もおすすめです。一方で、白砂糖や高GI値の精製された炭水化物、トランス脂肪酸、食品添加物などは控えめにし、血糖値の急激な変動や腸内環境の悪化を防ぐよう心がけましょう。
このように、さまざまな食品をまんべんなく摂ることで、体調を整え不定愁訴の改善につながります。
運動
無理なく継続できる軽めの有酸素運動やストレッチ、筋トレ、リラクゼーションを組み合わせるのが効果的です。具体的には、ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を1回10~50分、週2回以上続けることで、更年期を含む不定愁訴の症状が改善したという報告があります。また、首や肩こり、腰痛、冷え、しびれ、便秘、不眠などの症状には、部位ごとのストレッチやマッサージ、骨盤周辺の筋肉をほぐす運動も有効です。
継続的な運動は全身の血行を促進し、体温の上昇につながります。その結果、痛みやこり、しびれといった不定愁訴の症状が約75%改善したという報告もあります。無理のない範囲でウォーキングやストレッチ、筋トレなどを取り入れ、体をほぐしてリラックスする時間も意識しましょう。自分に合った運動を日常生活に取り入れることで、不定愁訴の症状緩和が期待できます。
精神面での取り組み
不定愁訴の背景にはストレスや自律神経の乱れが深く関係しています。心のケアを重視することで、症状の緩和や再発予防が期待できます。
まず、日常生活でストレスを自覚し、適切に発散する習慣を持つことが大切です。趣味や外出、気の合う人との会話など、心が安らぐ時間を意識的に確保しましょう。ヨガやマインドフルネス、深呼吸などのリラクゼーション法を取り入れると、交感神経の過剰な緊張を和らげ、副交感神経の働きを高める効果が得られます。
また、悩みや不安を一人で抱え込まず、身近な人や専門家に相談する姿勢も重要です。自分の状態を言葉にして整理するだけでも、心の負担が軽減される場合があります。
うつ病を改善するセルフケア
うつ病を改善させるには、上手に心を休ませてあげることが重要です。その際、肉体の健康にも同時に気を配りましょう。ここでは、早期で軽症を前提にしています。
ストレス状況下から抜け出す
うつ病の初期や軽症の段階では、ストレスの原因となっている状況から距離を置くことが重要です。まずは「休める時にしっかり休む」を心がけ、残業を減らしたり、休日や有給休暇を活用して十分な休養を取るようにしましょう。頭を休ませて考えすぎないよう意識し、仕事や家庭などでストレスが強い場合は、業務量の調整や環境の見直しも効果的です。ストレスをため込まず、発散できる機会(趣味、運動、音楽鑑賞など)を作りましょう。
肉体を整える
肉体の健康を保つことは、心の回復にも直結します。規則正しい生活リズムを意識して、決まった時間に寝起きし、十分な睡眠を取ることが基本です。朝起きたら日光を浴びて体内時計をリセットし、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。また、ウォーキングやストレッチなどの軽い運動は、セロトニンの分泌を促し抑うつ感を軽減する効果があり、睡眠の質向上やストレス発散にも役立ちます。無理のない範囲で体を動かし、疲労や睡眠障害など身体のサインにも注意を払いましょう。
一義流気功では、どうやって取り組むの?

潜在意識から情報を引き出す
自分自身の潜在意識は、心身を根底から詳細に把握しています。何がどうなって不定愁訴が出ているのか、うつ症状が出ているのか、外部から見ても本人が考えても解りませんが、潜在意識は状況の全てを理解しています。ですからまず、症状がどういった種類のものか、何が原因なのか、を全て明らかにします。それに沿って、気功治療の内容、日常生活での取り組みが導き出されます。
まとめ
不定愁訴とうつ病の初期症状は、身体的・精神的な不調が重なるなど共通点が多く、区別が難しい場合があります。不定愁訴は主に原因がはっきりしない身体の不調が中心で、検査でも異常が見つかりません。一方、うつ病では「気分の落ち込み」「何をしても楽しくない」などの精神的な症状が強く現れます。これら症状が2週間以上続き日常生活に支障が出る場合は、うつ病である可能性が高まります。
どちらの場合も、生活習慣の見直しやストレス対策、十分な休養、バランスの良い食事、適度な運動などセルフケアが重要です。特にうつ病は、無理をせず心身を休ませることが回復の第一歩となります。
不定愁訴もうつ病も、医療だけでなく日々のセルフケアや周囲の理解・支援が回復に大きく関わります。自分の体と心の変化に気づき、無理をせず、必要なときには専門家に頼ってください。
小池義孝の本
『知るだけで防げる うつの本』は、異常反応と心の毒との関係性を説明。『忘れたい過去が最短1分で消える!』は心の毒を自分で消すワークをご紹介しています。
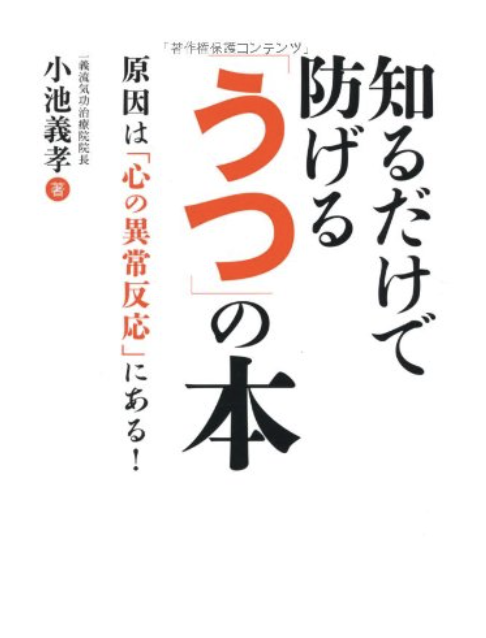
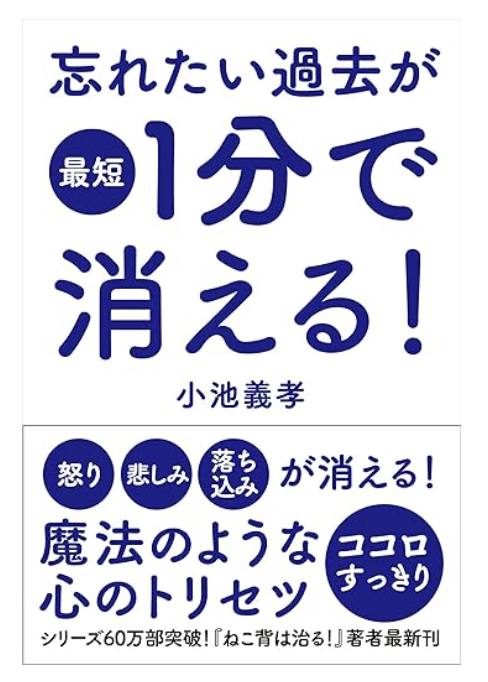
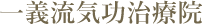
公式HP https://ichigiryu.com/about/
住所〒116-0002 東京都荒川区荒川 6-52-1 1F
電話番号03-6427-7446 / 090-6499-9762(直通)
営業時間午前10時~午後8時(電話受付:午前10時~午後7時)
コメント